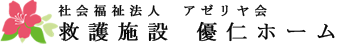・救護施設は全国に186か所、都内には10か所あります。
・救護施設は生活保護法に基づく、自立支援のための施設です。
・身体や知的、精神上に障がいがあり、経済的な問題も含めて日常生活を送るのが困難な人たちが入所し、持っている能力を発揮しながら、健康で安心して生活を送ることができる施設です。
・地域における福祉の拠点として、生活困窮者支援や地域公益活動などの取り組みを行っています。
法的位置づけ (生活保護法第38条第2項)
「救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。」

救護施設を利用する方
福祉事務所から入所が必要と判断された方となります
・生活保護を受けている方。
・身体や知的、精神に障がいをお持ちの方、またそれらの障がいを重複して持つ方、依存症の方、ホームレスの方など、多様で複合的な課題があり、経済的な問題も含めて日常生活を送るのが困難な方
優仁ホームで実施している事業
近年、救護施設は“地域におけるセーフティーネット”や、“通過施設”として、他施設などへの移行支援を実践しているほか、生活困窮者支援など地域貢献活動にも力を入れています。
- 入所事業(定員100名の施設入所事業・作業訓練)
- 居宅生活訓練事業(訓練アパート3室)
- 保護施設通所事業(通所・訪問・電話訪問ほか)
- 一時入所事業
- その他(生活困窮者就労訓練事業・地域公益活動・地域貢献事業ほか)
入所について
救護施設は生活保護法に基づく施設であり、救護施設への入所の必要性は福祉事務所が判断します。
そのため入所申し込みは福祉事務所が窓口となります。
- 福祉事務所へ入所相談
- 施設見学
- 入所申し込み(福祉事務所から優仁ホームへ)
- 入所判定会議(優仁ホームにて実施)
- 一時入所(体験入所)
- 入所
退所について
通過施設としての役割
お元気な方であれば、訓練を経てアパートなどに退所される方がいる一方、心身の状況により病院に入院される方、高齢者施設などに移られる方、様々な理由で長期的に当施設で生活されている方もおられます。
退所にあたっては、利用者の意向を伺いながら、ご家族、福祉事務所や医療機関など関係機関で十分な検討を行いながら進めていくことになります。
退所先の一例
- アパート
ひとり暮らしの実現による退所。
アパート生活移行者の多くが、当施設の保護施設通所事業を活用し、ひとり暮らしを継続しています。 - 病院
心身の状況により、医療が必要となり施設生活が困難となった場合 - 障がい者関係施設
本人の心身状況や意向などによるもの。
障がい者グループホーム ほか - 高齢者施設
65歳以上で介護などが必要な場合など。
養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・サービス付高齢者住宅・有料老人ホーム ほか - その他
他の救護施設・日常生活支援住居施設 ほか
退所先の実例
過去3年間の退所先の実例をご紹介いたします。
| 令和4年度(9名) | 令和5年度(7名) | 令和6年度(15名) |
|---|---|---|
| アパート 2名 養護老人ホーム 1名 特別養護老人ホーム 1名 グループホーム 1名 病院 3名 その他 1名 | アパート 2名 養護老人ホーム 2名 特別養護老人ホーム 0名 グループホーム 0名 病院 2名 その他 1名 | アパート 2名 養護老人ホーム 1名 サービス付き高齢者住宅1名 特別養護老人ホーム 0名 グループホーム 1名 更生施設 1名 病院 6名 その他 4名 |